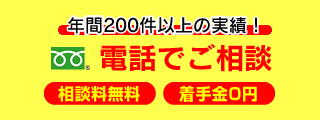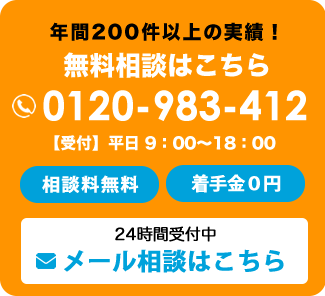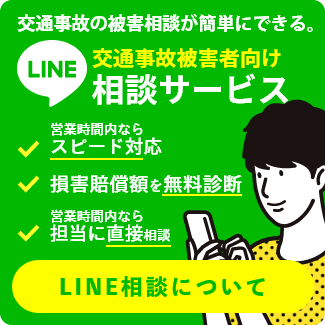交通事故に遭った際に後遺障害が残り、それによってこれまで従事していた仕事に支障が生じたり、続けることができなくなったりした方、ましてや重度な障害を負われた方であれば、働くこと自体ができなくなった方もいらっしゃることでしょう。この先の仕事についてどうしていくのか不安を抱えていることとお察しいたします。
このような場合に、交通事故に遭わなければ得られていたであろう収入と、事故後の収入との差額を加害者に請求することができる「逸失利益」という補償があります。これは後遺障害が認定された場合の賠償項目となります。
ここでは、交通事故の後遺障害によって生じる「逸失利益」について解説していきます。
逸失利益とは、減収発生を前提に加害者へ請求する補償です
逸失利益とは、交通事故によって働けなくなったり労働能力が低下してしまったりしたときに発生する将来の減収分のことです。
交通事故で後遺障害が残ると、身体のさまざまな部位が不自由になってそれまでのように効率よく働くことができなくなるので、給料が下がったり退職を余儀なくされたりして、減収が発生すると考えられるため、逸失利益は減収発生を前提としたものといえます。
逸失利益には2種類あり、交通事故で後遺障害が残ったときには後遺障害逸失利益を、死亡したときには死亡逸失利益をそれぞれ加害者に請求することができます。
後遺障害等級に応じた減収は、後遺障害逸失利益
事故により後遺障害が残った場合の逸失利益のことをいいます。事故で後遺障害を負ってしまうと、後遺障害の程度により労働自体が全くできないことや、その一部しかできなくなることあります。
労働ができなくなった度合いに応じ、将来得られるはずであった収入金額を逸失利益として請求することができます。
1年間の基礎収入×労働能力喪失率×労働能力喪失期間(ライプニッツ係数)
ライプニッツ係数とは、将来にわたって発生する収入を一括で受け取ることによって発生する「中間利息」を控除するための数値のことです。将来のお金を現在受け取るため、将来のお金の価値を現在に引き戻すことになるのです。
損害金を計算するときに余分な利益を差し引く必要があり、その調整のために用いられます。ライプニッツ係数は年数ごとに対応した数値が決まっているので、ケースごとに適切な数字をあてはめて計算します。
死亡事故によって発生する減収は、死亡逸失利益
事故により死亡した場合に発生する逸失利益のことです。死亡すると、事故後にできるはずであった労働が全くできなくなるため、その分の収入について補償されます。
ただし、事故後にかかるはずであった生活費が不要になることを考慮するため、収入の100%が支払われるわけではない(=生活費控除)ので、注意が必要です。
1年間の基礎収入×(1-生活費の控除)×労働能力喪失期間(ライプニッツ係数)
生活費の控除は、亡くなった方が家計を支える一家の支柱であるか、男性であるか女性であるか等によって基準となる控除率が異なります。
- 一家の支柱で、被扶養者が一人の場合…40%
- 一家の支柱で、被扶養者が二人以上の場合…30%
- 主婦、独身、幼児等を含む女性の場合…30%
- 独身、幼児等を含む男性の場合…50%
被害者が一家の支柱であれば被扶養者がいるため、ご自身の生活のために収入を使う割合が低くなると考えられており、一家の支柱の場合は扶養者の人数によって控除率が異なります。
ただし、女子年少者(概ね高校生くらいまで)につき、男女を合わせた全労働者の平均年齢を採用する場合は、生活費控除率を45%として算定します。
その一方、その他の方(一家の支柱とまでは言えない方や一人暮らしの方など)であれば、ご自身の生活のために収入を使う割合が高くなると考えられることが一般的です。
ただし、生活費控除率は、被害者の状況に応じて異なるため、必ずしも上記のとおり控除されるとは限りません。
逸失利益算定でポイントとなる、基礎収入額について状況別に解説
逸失利益算定の根拠となる基礎収入は、事故前年度の収入をもとに算出することが原則ですが、給与所得者、個人事業主、学生等によって、それぞれ考え方が異なります。
ここでは、いくつか代表的な基礎収入の考え方をあげて詳しく解説していきます。
会社員(給与所得者)の場合
原則として事故前年の現実の年収(勤務先の発行する事故前年の源泉徴収票に記載された社会保険料や所や税金などを控除する前の金額)が基礎となります。
ただし、概ね30歳未満の若年労働者のうち、実際の年収が賃金センサスより低い方は、原則として症状固定時の賃金センサスの全年齢平均賃金を基礎収入とします。
また、30歳以上であっても、たまたまその時に就職活動中で年収が少なかった場合や、それなりの学歴や実力を持っていたけれど、たまたま事故当時は働いていなかった場合など、平均賃金を得られる蓋然性があれば、基礎収入として賃金センサスの平均賃金が認められることがあります。
会社役員の場合
会社役員の基礎収入は、事故前年の役員報酬のうちの労働の対価相当部分とされるのが原則です。
会社役員の受け取る役員報酬には、役員報酬が労働の対価である場合と、経営の結果による利益配当である場合の2つの性質があります。
このうち、会社の利益配当相当の部分については不労所得であり、その地位にある限り事故による収入減はないと考えられるため基礎収入に算入できません。
もっとも、後遺障害が残ったことが理由で役員を解任された場合や死亡して利益配当分が遺族に承歴されない場合は、利益配当相当部分も含めた役員報酬を基礎収入とすることができる場合があります。
個人事業主・自営業者の場合(事業所得者)
個人事業主や自営業者といった事業所得者の基礎収入は、事故前年の確定申告書の申告所得額から必要経費を控除した所得金額を基準とし、(事故前年の売上-必要経費)×寄与分(率)の計算式に当てはめて算定されます。
ただし、事業所得者や自営業者の場合には確定申告が赤字のケースがあり、この場合には注意が必要です。
赤字申告の自営業者であっても休業損害や逸失利益が認められることはありますが、その場合、「固定経費」分を基礎収入としたり、「業種別や年齢別の平均賃金」を使ったりして基礎収入を計算することがポイントです。
また、過少申告や無申告の場合、過少申告は実際はより多くの収入があること、無申告は収入があったことをそれぞれ立証できれば、基礎収入として認定される可能性があります。
また、死亡した場合に事故前年度が赤字であっても、亡くなったことによって将来にわたって稼げなくなったと考えられるため、死亡逸失利益は認められる傾向にあり、この場合は、確定申告をしていなくても、実際の所得が証明できれば、死亡逸失利益を請求できる可能性があります。
主婦(夫)の場合
主婦(夫)のように、実際に賃金を受け取っていない家事従事者の場合でも、家事労働には一定の経済的価値があると考えられていますので、判例においても金銭的に評価できるとされています。
家事従事者(性別・年齢問わず、家族のために家事労働に従事する方)の方が事故に遭った場合、後遺障害が残るとこれまで通りの家事ができなくなるだけでなく、子供がいる方であれば育児にも支障が出てしまう可能性があります家事や育児が可能であったとしても、痛みなどを堪えながら従事することになるため、逸失利益を補償される必要があるのです。
家事従事者の基礎収入は、賃金センサスの「全年齢の女性の平均賃金」を基礎収入とします。パートタイム労働を行うなどして一定の収入がある兼業主婦の場合は、現実の収入が平均賃金を上回っている場合は現実の収入で算定し、平均賃金を下回っている場合は平均賃金とし、どちらかが高い方が基礎収入として採用されます。
また、補助的な主婦や高齢の主婦の場合は、年齢別の女性の平均賃金を採用して、基礎収入を減額することもあります。
高齢者・年金生活者の場合
就労している高齢者の場合、基本的に現実の実収入を基礎収入とします。
働いていない方でも、就労意欲があり、実際に就労する能力と蓋然性があった場合や、家族のために家事労働をしているといったケースでは、逸失利益が認められる可能性があります。
高齢になると、一般的に若年者よりも労働能力が落ちると考えられるため、基礎収入の算定には業種別や男女別の平均賃金を割合的に減額して適用するなど、適宜減額されるケースが多くなります。
ただし、年金生活者の場合、後遺障害が残っても年金が減額されることはないため、後遺障害逸失利益は認められませんが、死亡した場合は将来受給できたであろう年金分を受給できなかったと考えられるので死亡逸失利益は認められる可能性があります。
判例においても、遺族年金や障害年金(加給分)など、ごく一部の年金は逸失利益性を否定されていますが、大半の年金(高齢年金や障害年金、退職年金など)は逸失利益が認められる傾向にあります。
幼児・子供、学生の場合
幼い子供や学生は、社会人のように給与を受け取っている訳ではありませんが、将来就職して収入を得る可能性があることから、後遺障害が残存した場合でも、死亡した場合でも逸失利益が認められています。
基礎収入は、賃金センサス男女別労働者・学歴計・全年齢の平均賃金となります。しかし、これで計算すると、女児よりも男児の方が、逸失利益が高く不公平になってしまうことから、最近の判例では、女児が被害者となっている場合の基礎収入を「男女の平均賃金」とする例が増えてきています。
死亡事故のケースでは、女性の場合の死亡逸失利益の生活費控除率が低いことから、男児よりむしろ高額になる可能性もあります。
無職者・失業者の場合
逸失利益は、事故がなければ就労して得られたはずの収入ですので、事故当時が無職者であっても、就労の蓋然性が高かった場合には、失業以前の給与額や賃金センサスを基準にした金額を基礎収入として認められる可能性があり、計算式は一般的な会社員などと同様に、基礎収入×労働能力喪失率×ライプニッツ係数で計算します。
これに対し、不動産収入や株式配当で生活している人の場合、身体が不自由になったことによる減収が発生しないため、逸失利益は認められません。
後遺障害等級に応じて定められた、労働能力喪失率とは?
労働能力喪失率とは、健常時の労働能力を100として、後遺障害を負った場合にどれくらいの割合で労働能力が減少し、どの程度失われたのかを数値化したものをいい、等級が重くなるにつれ労働能力喪失率は高くなります。
自賠責保険後遺障害等級表によれば、後遺障害等級第1級は労働能力喪失率が100%、後遺障害等級第14級であれば、労働能力喪失率は5%となります。
ただし、醜状障害や鎖骨の変形障害、嗅覚障害、味覚障害等においては、保険会社が労働能力の喪失を否定してくることも多く、労働能力喪失率が大きな争点となることがあります。
労働能力喪失率は、後遺障害の等級に左右されるため、それぞれの後遺障害に応じた適正な等級認定を受けることが非常に重要です。
逸失利益に大きな差が出る?適正な労働能力喪失期間について
労働能力喪失期間とは、後遺障害または死亡によって労働能力を失う期間のことをいいます。
一般的に人が働ける年齢の上限を67歳と仮定し(就労可能年数)、症状固定時または事故発生時からの年数と後遺障害の程度に応じて逸失利益が認められます。
裁判上も、労働能力喪失期間の始期と終期を決めることで、交通事故による後遺障害の労働能力喪失期間を数値化し算定しています。
会社員や会社役員、自営業者などの給与所得者や主婦などの場合、始期は症状固定日、終期は67歳とされることが原則です。
ただし、被害者の年齢や性別、その他個別事情によって労働能力喪失期間は変動し、むちうち症の場合は、第12級で10年程度、第14級で5年程度とされることが一般的です。
その他にも子供や大学生、高齢者等については、少し異なる考え方をします。
18歳未満の子供、大学生の場合
幼児や大学入学前の未就労者の場合は、原則として始期を18歳、終期を67歳までの49年間とします。
大学生や高等専門学校在学中の場合には、始期はその卒業時の年齢(4年制の大学生の場合は22歳が一般的)で、終期については67歳とされています。
高齢者の場合
症状固定時の年齢が既に67歳を超える高齢者の場合には、平均余命の2分の1が労働能力喪失期間と考えられています。
ただし、被害者が既に67歳までの期間が短い高齢者の場合や、67歳を超えても働き続ける漠然性がある場合などもあるため、このような場合には、「67歳までの年数」と「症状固定時または死亡時の平均余命の2分の1」を比べて長い方を就労可能年数として計算することもあります。
労働能力に影響がない?逸失利益を否定されやすい後遺障害とは
後遺障害が認定されたとしても、労働能力に影響がないと考えられる場合、加害者側(保険会社側)が逸失利益を否定してくる可能性があります。
以下でその代表的なものを挙げます。
外貌醜状、醜状痕
外貌醜状とは、顔や頭、首などの露出する部分にやけどやアザ、線状痕や陥没などの醜状が残る後遺書障害です。
腕や脚などに醜状が残った場合にも、面積やその程度に応じて等級が認定されます。これらの後遺障害が残っても、身体的な機能の低下がないことから、労働能力は失われないと考えられるため逸失利益が否定されやすいのです。
ただし、モデルや俳優など人前に出る職業の場合や営業マンなどのケースでは、外貌醜状によって仕事が制限されたり、影響が出たりすることがあるため、そのような場合には逸失利益が認められる可能性があります。
醜状障害の場合、本当に労働能力に影響しないのかを具体的に検討していくことが肝要です。当事務所の解決事例でも、醜状障害で14級と認定され195万円の提示がされた事例について異議申立を行った結果、等級は第9級に改められることとなり、逸失利益を保険会社から否定されたケースで、将来従事する予定の職業の内容や学生時代に1度モデルになった経験があったことなどを立証し、195万円の提示金額が最終的に3116万円に増額したという解決事例もあります。
足の短縮障害
片脚が1センチ以上3センチ未満短縮した場合は、足の短縮障害として後遺障害が認定されますが、労働能力への影響が小さく労働能力喪失がないとして逸失利益を否定されやすい傾向にあります。
味覚障害、嗅覚障害
交通事故によって味覚がわからなくなったり、嗅覚を失ったりするケースもありますが、調理師でもない限り労働能力に影響があまりないと考えられる傾向にあるため、逸失利益を否定されやすいといえます。
歯牙障害
歯牙障害とは、顔面などを負傷し歯を失う後遺障害です。現代の医学では、入れ歯やインプラントなどで普通通りに生活できるように治療できるため、労働能力には影響がないとして逸失利益を否定されやすいことがあります。
脾臓の摘出
脾臓を摘出した場合にも後遺障害が認定されますが、日常生活や仕事にほとんど影響しないケースが多いので、逸失利益を否定されやすいです。
生殖器の障害
交通事故で生殖器に影響がおよび子供を作れない身体になってしまうケースがありますが、労働能力とは無関係であると考えられる傾向にあるため、逸失利益を否定されることが多いです。
 精巣損傷後の睾丸の委縮による後遺障害13級相当により519万円を獲得した事案
精巣損傷後の睾丸の委縮による後遺障害13級相当により519万円を獲得した事案
鎖骨、脊柱の変形
鎖骨や脊柱が変形した場合にも、それぞれ後遺障害が認定されますが、労働能力には影響しないことが多く、逸失利益を否定されやすいです。
脊柱の圧迫骨折が存在する場合は、後遺障害11級(圧潰率によって6級)となる場合がありますが、同じ等級であっても、後遺障害の認定が痛みも含めるか否かで、その後の示談交渉の成否が大きく変わってくるので、脊柱の変形だけで逸失利益が否定されるケースでも、背骨の痛みがある場合は背骨の痛みを含めた後遺障害を獲得することが重要となります。
 鎖骨を骨折し鎖骨変形障害で920万円を獲得、賠償金が3倍以上に増額した事案
鎖骨を骨折し鎖骨変形障害で920万円を獲得、賠償金が3倍以上に増額した事案
以上のように、後遺障害が残っても逸失利益を請求できなかったり減額されたりするケースは意外と多いです。
後遺障害が残って相手の保険会社が逸失利益を否定しても、諦める必要はありません。粘り強く立証を行うことで大きく結果が異なることもありますので、諦めずに弁護士へご相談することをお勧めします。
減収がない場合は、逸失利益を請求できない?

逸失利益は、減収発生を前提とした補償であると述べましたが、後遺障害が残っても減収が発生しない方もいらっしゃいます。
昭和42年11月10日判決では、「逸失利益は事故による減収を前提とするものであるから、実際に減収が発生していなければ、逸失利益は発生しない」と判断しており、今でもこの考え方が踏襲されています。
そこで、減収がない場合は、後遺障害逸失利益を請求できないというのが原則です。
具体的に減収が発生しない場合には以下のようなケースが考えられ、実際に、任意保険会社は、「実際の損害がないのだから、後遺障害逸失利益を否定する」という対応が多くみられます。
- 軽微な後遺障害で、以前と同様の仕事ができている場合
たとえば、むちうちによる神経症状などの軽微な後遺障害の場合には、それまでと変わらず仕事を続けることも可能です。以前と同じ仕事をしているのですから、当然減給にはなりません。 - 会社が特別な配慮してくれている場合
以前の仕事ができなくなったとしても、会社が配慮してくれて、できる仕事を与えてくれるケースがあります。そして異動や配置転換があっても必ずしも減給になるとは限らないので、以前よりは仕事が軽くなっても給料が減らないことがあります。 - 本人の努力によって減収が発生しないようにしている場合
本来であれば後遺障害によって動きにくくなり、仕事の継続が難しくなっているはずですが、本人の特別の努力によって減収が発生しないようにしているケースがあります。 - 会社役員の場合
交通事故の被害者が役員の場合にも、減収が発生しないことが多いです。役員は、もともと労働の対価としての賃金だけではなく、会社経営に携わっていることによって発生する利益配当として会社から給料を受け取っているからです。 身体が動かなくなっても利益配当に影響はないので、利益配当部分については減収になりません。
ただし、減収がない場合であっても、「特段の事情」を主張立証することで、逸失利益が認められる可能性があります。
- 収入が減少しないように本人が特別な努力を払っている場合
- 現在は減少していないが将来的に昇進、昇給、転職などで不利益を被る可能性がある場合 など
実際の裁判においても、このような特段の事情を立証することで、後遺障害逸失利益が認められたケースが多く存在しています。
当事務所においても、症状固定後に現実の収入現象がないケースで、被害者の方ご本人が行っている「本人の特別な努力」を十分にヒアリングし、報告書等にまとめて立証をすることにより、逸失利益をいくつも獲得しております。
介護を要する後遺障害が残ると、将来介護費が認められる
将来に渡って介護が必要な状態になってしまった場合、その際にかかる介護費用は損害として請求することができます。
基本的に介護が必要となるのは、後遺障害等級第1級や第2級の重度の障害ですが、第3級以下でも高次脳機能障害などの場合は認められることがあります。
但し、高次脳機能障害などの場合には身の回りのことをある程度自分でできることもあるため、常時付き添いの必要はないとして、1日あたりの金額を抑えられる傾向があるなど、賠償額は個別事案に応じて算定されますが、ヘルパーなどの職業付添人は実費全額、近親者付添人は1日につき8,000円前後が目安となります。
介護が必要な期間として賠償額算出の対象になるのは、原則平均余命までとされます。
加えて、介護が必要な期間すべてを職業付添人、もしくは近親者いずれかのみの費用で算出しなければいけないことはなく、個別の状況ごとに双方を組み合わせて算定するのが一般的です。
年間の介護費用×平均余命までの期間に対応するライプニッツ係数
ライプニッツ係数は、逸失利益の計算の時に用いられるものと同じで、「中間利息」を控除するための数値のことを指します。年数ごとに数値が決まっているので、個別事情を考慮し、適切な数字をあてはめて算定を行います。
また、2名以上の介護者が必要な場合には、人数分の介護費用が損害として認められる場合もあります。
まとめ
基本的に会社員などの給与所得者や、給与所得がなくとも、他者のために家事労働を行う主婦(夫)、就労の蓋然性のある学生や無職者については、後遺障害等級に応じた逸失利益が認められますが、不動産の家賃収入等で生活する不労所得者や年金生活者の場合、後遺障害が認められても収入が減少しないケースもあり、何らかの損害もない以上、逸失利益は認められないことがほとんどです。
ただし、本人の特別な努力によって何とか減収を防いでいる場合などには、労働能力低下による影響が出ているので、実際の減収が発生していなくても逸失利益が認められるべきであり、また、今すぐには減収が発生しなくても、将来的に昇進や昇格が難しくなったり転職に際して不利益な取扱いを受ける可能性が高くなったりしたのであれば、やはり逸失利益が発生していると考えられます。
後遺障害が残っても逸失利益を請求できなかったり、減額されたりするケースは意外と多く、被害者の職種や状況など個別事情を細かく精査することで逸失利益を請求できる可能性があります。
また、示談交渉段階で後遺障害逸失利益を否定されても、裁判を起こし、慰謝料を増額して支払ってもらえるケースもありますので、後遺障害が残って相手の保険会社が逸失利益を否定してきても、諦める必要はありません。
後遺障害や死亡事故の逸失利益は、高額になることも多く、示談交渉や裁判において大きな争点となる項目の1つですので、それぞれの方の症状に応じた適切な解決のために、示談の前に一度弁護士にご相談いただくことをおすすめします。
アジア総合法律事務所では、福岡、九州を中心に全国で発生した交通事故に対応していますので、逸失利益について納得できない場合には是非ともご相談ください。