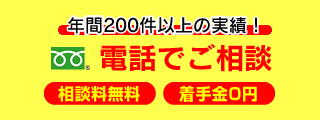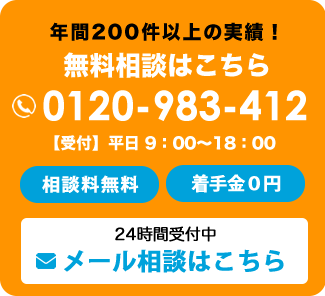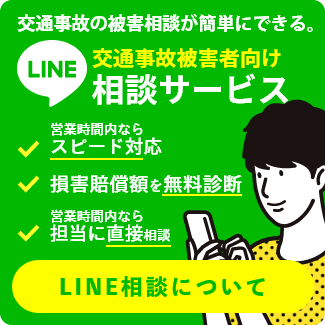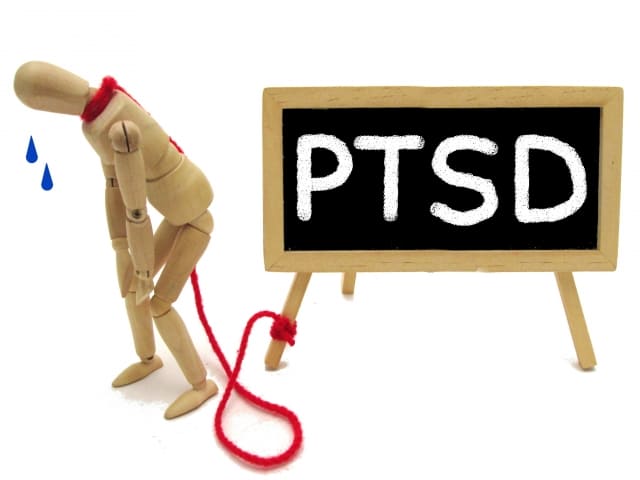
非器質性精神障害とは、脳の損傷を伴わない精神障害のことを指し、PTSD(心的外傷後ストレス障害)やうつ病などがこれにあたります。
これらは、交通事故による強い恐怖やストレスによって発症する場合があります。
非器質性精神障害の立証には、次の3つの基準が用いられることが多いです。
厚生労働省の定める診断基準
精神症状の状態に関する判断項目
- 抑うつ状態
ア 持続するうつ気分(悲しい、寂しい、憂うつ、希望がない、絶望的である等)
イ 何をするにもおっくうになる、それまで楽しかったことに対して楽しい感情がなくなる
ウ 気が進まない状態
これらの状態にあるか。 - 不安の状態
全般的不安や恐怖、心気症、強迫など強い不安が続き、強い苦悩を示す状態にあるか。 - 意欲低下の状態
すべてのことに対して関心が湧かず、自発性が乏しくなる、自ら積極的に行動せず、行動を起こしても長続きしない、口数も少なくなり、日常生活上の身の回りのことにも無精となる状態にあるか。 - 慢性化した幻覚・妄想性の状態
自分に対する噂や悪口あるいは命令が聞こえる等実際には存在しないものを知覚体験すること、自分が他人から害を加えられている、食べ物に毒が入っている、自分は特別な能力を持っている等、内容が間違っており、確信が異常に強くて訂正不可能であり、その人個人だけに限定された意味付けなどの幻覚、妄想を持続的に示す状態にあるか。 - 記憶または知的能力の障害
自分が誰であり、どんな生活史を持っているかをすっかり忘れてしまう生活史健忘や生活史の中の一定の時期や出来事のことを思い出せない状態、非器質性の知的能力の障害としては、解離性障害=心因性障害がある。 日常身辺生活は普通にしているのに改めて質問すると自分の名前を答えられない、年齢は 3 歳、 1 + 1 = 3 のように的外れな回答をするような状態、カンザー症候群、仮性痴呆が認められるか。 - その他の障害(衝動性の障害、不定愁訴等
上記の①~⑤に分類出来ない症状、多動つまり落ち着きのなさ、衝動行動、徘徊、身体的な自覚症状や不定愁訴が認められるか。
能力に関する判断項目
- 身辺日常生活
入浴や更衣等、清潔保持を適切にすることができるか。 規則的に十分な食事をすることができるか。 - 仕事・生活に積極性・関心を持つこと
仕事の内容、職場での生活や働くことそのもの、世の中の出来事、テレビ、娯楽等の日常生活等に対する意欲や関心があるか否か。 - 通勤・勤務時間の厳守
規則的な通勤や出勤時間等、約束時間の遵守が可能か。 - 普通に作業を持続すること
就業規則に則った就労が可能か。 普通の集中力・持続力を持って業務を遂行できるか。 - 他人との意思伝達
職場において上司・同僚等に対して発言を自主的にできるか。 他人とのコミュニケーションが適切にできるか。 - 対人関係・協調性
職場において上司・同僚と円滑な共同作業、社会的な行動ができるか。 - 身辺の安全保持、危機の回避
職場における危険等から適切に身を守れるか。 - 困難・失敗への対応
職場において新たな業務上のストレスを受けたとき、ひどく緊張したり、混乱することなく対処できるか。 どの程度適切に対応ができるか。
ICD-10
交通事故に遭い、PTSDの症状が出た場合、上記のようなICD-10に基づいた診断を医師にお願いしすることとなります。
ICD-10は、次の診断基準で構成されています。
- 自ら生死に関わる事件に遭遇したり、他人の瀕死の状態や死を目撃した体験などの破局的ストレス状況に暴露された事実があること
- 自分が「危うく死ぬ 、重傷を負うかも知れない」という体験の存在
- 通常では体験し得ないような出来事
- 途中覚醒など神経が高ぶった状態が続く
- 被害当時の記憶が無意識の内に蘇る
- 被害を忘れようとして感情が麻痺する。そのために回避の行動を取る。
- 外傷の出来事から1ヵ月後の発症、遅くとも6ヶ月以内の発症
- 脳の器質性精神障害が認められないこと
DSM-Ⅳ
DSM-Ⅳは、A~Fの判断基準で構成されています。
A. 以下の2条件を備えた外傷的出来事の体験がある。
- 実際にあやうく死亡したり、又は、重傷を負ったりするような(あるいは危うくそのような目に遭いそうな)出来事、あるいは自分もしくは、他人の身体への切迫した危機状況を体験し、目撃し、直面した。
- 患者が強い恐怖心や無力感や戦慄という反応を示している。
B. 外傷的な出来事が、次のいずれかの形で、繰り返し再体験され続けている。
- その出来事の記憶が、イメージや考えや知覚などの形で、追い払おうとしても反復的に襲ってくること。
- その出来事についての悪夢を繰り返し見ること。
- あたかも外傷的な出来事が繰り返されているかのように行動したり、感じたりすること(その出来事を再体験している感覚、錯覚、幻覚や、覚醒状態や薬物の影響下で起こるフラッシュバックを含む)。
- 外傷的出来事の一つの側面を象徴する、あるいはそれに似通った内的・外的な刺激に直面した時に、強い心理的苦痛が生じること。
- 外傷的出来事の側面を象徴するような、あるいはそれに類似する内的又は外的な刺激に対し、生理的反応を起こすこと。
C. 当該の外傷に関係する刺激を執拗に避け、全般的な反応性の麻痺が執拗に続く状態が(その外傷を受ける前にはなかったのに)、以下の3項目以上で見られること。
- その外傷に関係する思考や感情や会話を避けようとすること。
- その外傷を思い起こさせる行動や場所や人物を避けようとすること。
- その外傷の要所が思い出せないこと。
- 重要な行動に対する関心や、その行動へのかかわりが著しく減少していること。
- 他者に対する関心がなくなった感じや、他者と疎遠になった感じがすること。
- 感情の幅が狭まったこと(愛情を抱くことができないなど)
- 未来の奥行きが狭まった感じがすること(出世や結婚、子ども、通常の寿命を期待しなくなるなど)。
D. 高い覚醒亢進状態を示す症状の持続(その外傷を受ける前にはなかったのに)、以下の2項目以上で示されること。
- 入眠や睡眠状態の持続が困難であること。
- 激しやすさや怒りの爆発があること。
- 集中が困難であること。
- 過度の警戒心が過度に見られる。
- 驚愕反応が極端
E. 障害(基準B、C、Dの症状)が1ヵ月以上持続すること。
F. 障害のため、社会的、職業的に、あるいはその他の重要な領域で、臨床的に著しい苦痛や機能の障害があること。
次の点を明確にすること
- 急性:症状の持続期間が3ヵ月未満の場合
- 慢性:症状の持続期間が3ヵ月以上の場合
- 発症遅延型:発症がストレス因から少なくとも6ヵ月経過している場合
まとめ
非器質性精神障害の審査では、上記検査による判断基準のほかにも、改善可能性の有無が検討されます。
一般的に、非器質性精神障害は、原因を改善又は除去することで改善するものであると考えられているため、安易に後遺障害が認定されない傾向にあります。
むちうちなどの骨折を伴わない後遺障害の申請時には、受傷後約6か月を症状固定の目安とし、その時点で残存した症状について後遺障害等級申請を行うことが多いですが、非器質性精神障害の場合は受傷後約1年ほどは判断期間を設ける必要があり、時間がかかります。
非器質性精神障害(PTSD)の後遺障害の立証は非常に困難ですので、弁護士にご相談されることをおすすめします。